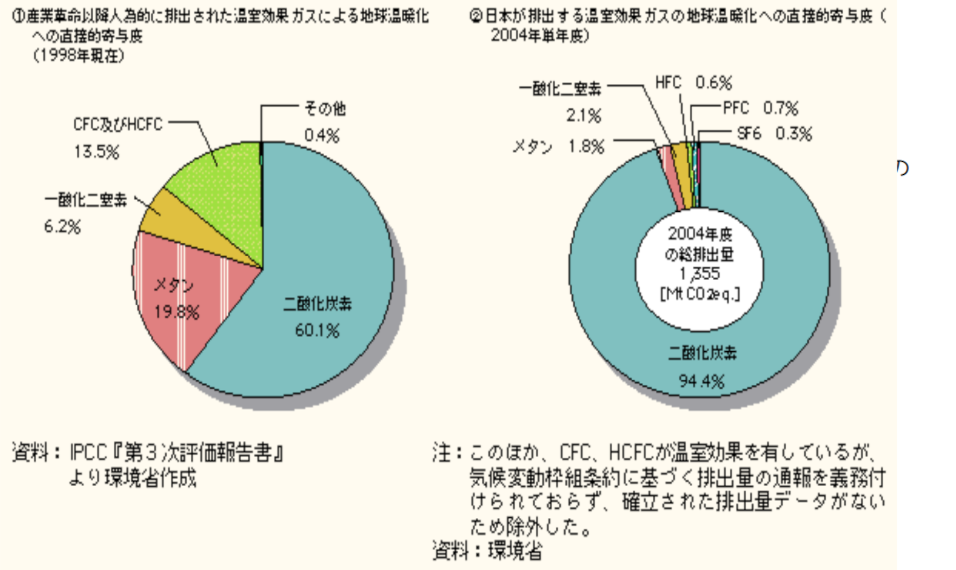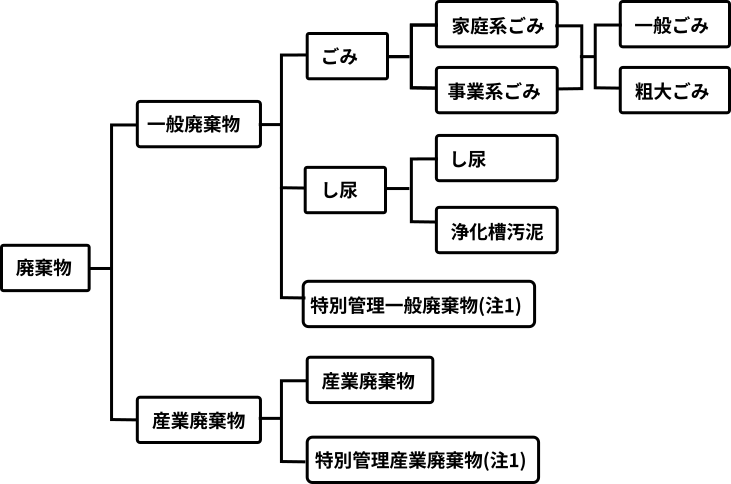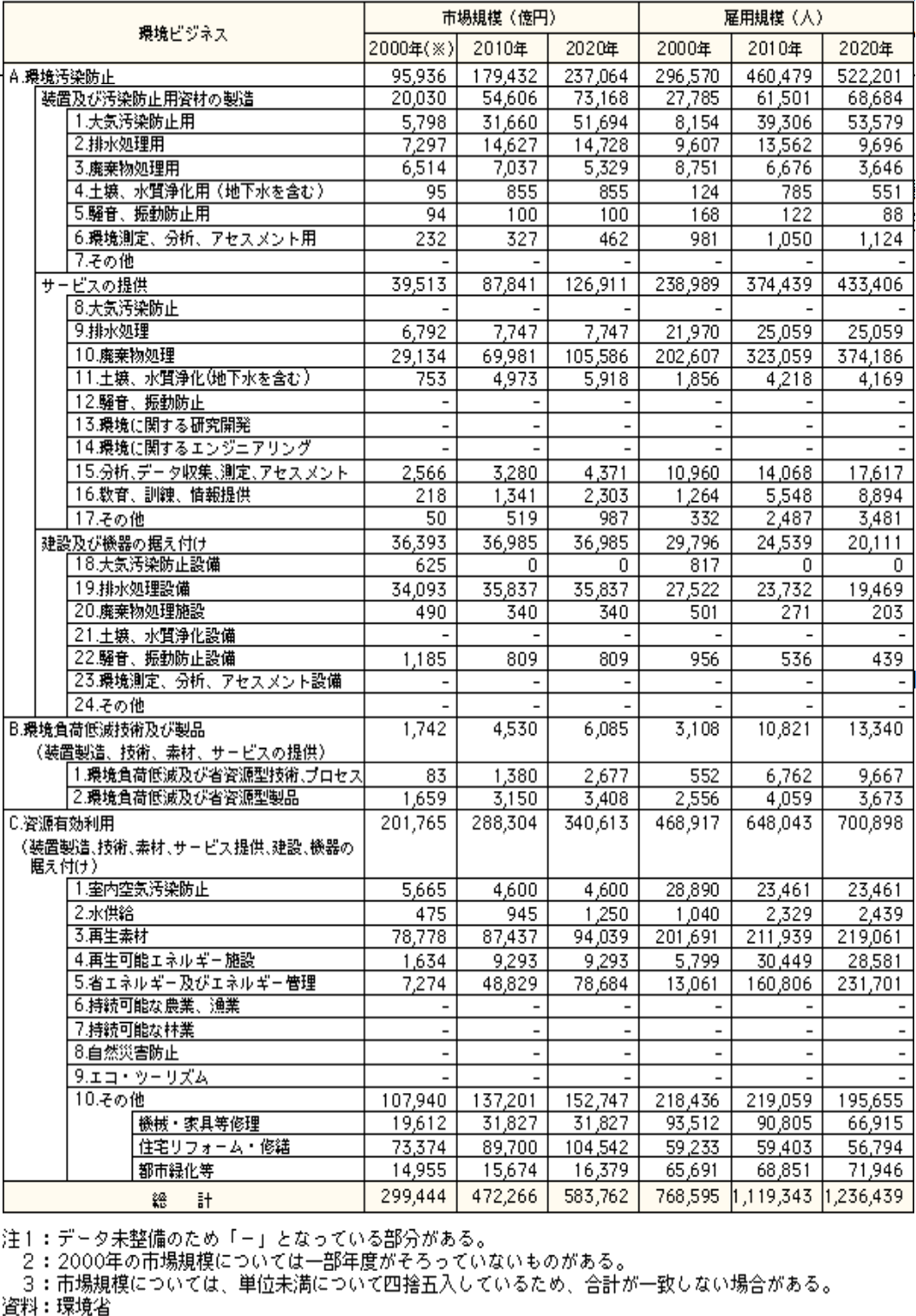現在、省エネルギー・二酸化炭素排出削減の為の種々の対策が推進されい
るがエネルギー供給面の対策として、電気事業者に販売電力量に応じて一定割合の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務付る
「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」 が、2003年に完全施行された。(表21.5 参照 )
表21.5 RPS制度の概要一覧表
| 項 目 |
主 な 内 容 |
| RPS制度とは |
Renewable Energy Portfolio Standard ないし Renewables Portfolio Standard の略称。電力小売業者に新エネルギーから発電した電気
(新エネ電気)の一定割合以上の引取りを義務付け,新エネ電気の導入促進
を図る。新エネ電気は証書によって取引きされ,自社の供給地域で新エネ電
気が不足する電力小売業者は,証書を購入することによって義務を達成する
ことができる。
|
| 根拠法 |
「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS
法)2002 年 5 月に国会成立,6 月公布,12 月に新エネ等電気の設備認定部
分の規定を施行,2003 年 4 月に引取義務部分の規定を施行し,法律が完全
施行された。 |
| 利用目標 |
経済産業大臣は,総合資源エネルギー調査会,環境大臣,その他関係大臣
の意見を聞いて新エネルギー電気の利用目標を定める。経済産業大臣は,利
用目標を考慮し,電気事業者に対し,毎年度,その販売電力量に応じて一定
割合以上の新エネ電気の利用を義務づける。
<利用目標>
単位:億 kWh/年
| 15年度 |
16年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
| 73.2 |
76.5 |
80.0 |
83.4 |
86.7 |
92.7 |
103.3 |
122.0 |
|
| 引取義務の対象者 |
一般電気事業者(電力会社),特定規模電気事業者(電力小売の新規参入
者),特定電気事業者(再開発地区など地域を限って小売事業を展開する事
業者)の 3 事業者。
|
| 義務の履行方法 |
電気事業者は,義務を履行するにあたって①自ら発電する,②他社から新
エネ電気を購入する,③他の電気事業者に義務を肩代わりせることができる
これにより電気事業者は,経済性やその他の事情を考慮して,最も有利な方
法を選択することが可能になる。
|
| 新エネ電気とは |
RPS 法は,新エネルギーとして,風力,太陽光,地熱,水力,バイオマス
その他政令で定めるものと規定して,これらのエネルギーから発電した電気
を新エネルギー電気としている。
|
| 新エネ電気の種類 |
風力発電,太陽光発電,地熱発電,水力発電,バイオマス発電の5発電が
新エネ電気になるが,今後,公布される政令等によって水力発電は,ダムな
しで,1,000 k W 以下のものとする,地熱発電は,地下の高温蒸気を減少さ
せる度合いの少ない再生可能性が高いものを対象とする等の制限が加えられ
る。
|
| 設備認定 |
新エネ電気を発電する者は,発電設備が基準に適合していることについて
経済産業大臣の認定を受けることができる。経済産業大臣は,バイオマスを
利用する発電設備については,予め関係大臣と協議する。設備認定の要件と
して,系統へ連係している新エネ電気の量が計算できる設備が必要となる。
|
| バイオマスの規定は |
RPS 法は,バイオマスについて,動植物に由来する有機物であってエネル
ギー源として利用できるもので,原油,石油ガス,天然ガス,石炭と,それ
らの製品を除くと規定している。この結果,バイオマスは,農業廃棄物,畜
産廃棄物,林業廃棄物,食品廃棄物,建築廃材,下水汚泥等からなり,製紙
業界の黒液も対象となる。
|
| 混焼の場合は |
熱量ベースの混焼比率に応じて新エネ電気の量をカウントする。混焼比率
の調査方法,計算方法,チェックの頻度等は今後,明らかになる見通し。
|
| 廃プラ発電の適用は |
廃棄物発電のうち廃プラスチックなど原油等から製造される製品を熱源と
するエネルギーについては現在まで結論を得ておらず,今回の政令では,廃
プラ発電は新エネ電気の対象から除外し,検討を継続することとなった。
|